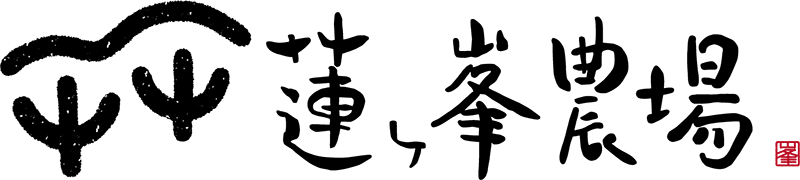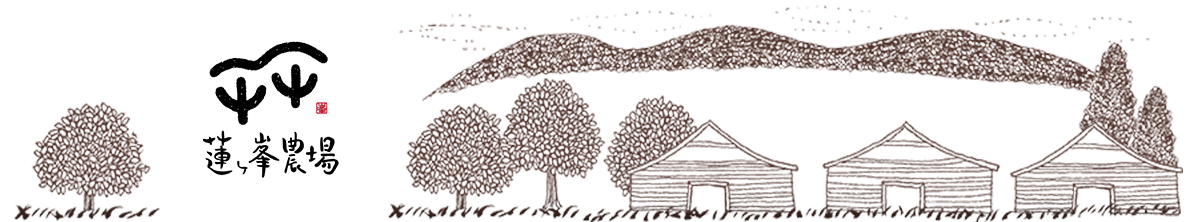純国産鶏「もみじ」と共に
蓮ケ峯農場は、創業当時より約30年間純国産鶏「もみじ」にこだわってきました。
日本の採卵鶏の95%以上は、外国鶏と言われています。外国鶏は産卵率もよく、安定しており、生産性に優れています。純国産鶏というのは、日本国内において幾世代にもわたって、交配を繰り返して育種改良を行い作出される実用鶏のことです。農家として、生産性はもちろん大切です。
しかし、農家だからこそ、「命の種を守っていく」ということも大切だと考えています。
これからも「もみじ」の飼育技術を極め、より良い環境づくりをしていきたい。鶏たちに蓮ケ峯農場にきて良かったと思ってもらえるように。

鶏飼いの原点に還るたまごから育てる烏骨鶏
鶏飼いという仕事が産業として成り立つために分業化が進みました。品種改良をする企業。雛を生産して実用鶏を販売する企業。実用鶏を飼育してたまごやお肉を生産する養鶏場。
この効率化したシステムの中では多くの犠牲が生じます。例えば、採卵鶏にオスは必要ありません。産まれてすぐに処分されます。その数は、日本だけでも年間2億~2億5千万羽と言われています。採卵鶏のオスは生育が遅く、肉鶏には適していません。
そこで蓮ヶ峯農場は新しい取り組みをはじめます。烏骨鶏の自家繁殖飼育です。オスは育てて肉としていただきます。メスはたまごを産んでもらいます。
お肉になる運命なら育てても同じでは?
すべての生きものは死を迎えます。種の進化、存続のために迎えなくてはなりません。人も同じです。最後は死ぬのです。その生きている時間をどう過ごすのか?
私たちはそこに意味があると考えています。
短い時間ですが、生きものらしく、鶏らしく生きてほしいのです。
食べるために飼育することを始めた人間は
飼育する生命の生き方や価値を認める必要があるのではないかと考えています。

烏骨鶏は体が小さく、品種改良がほとんどされていないことからそんなに多くのたまごを産むことができませんが、本能が強く残っていますので抱卵して雛を孵し育てることもできます。
それぞれの家庭の庭先で鶏が飼われていた古き良き時代。21日間ほとんど動かずに、静かにたまごを温め続ける健気な親鶏。無事に孵化した雛を連れて歩き、必死に外敵から子を守る親鶏の姿。その愛を受けて、少しずつ成長していく雛の姿。その時代の人は、当たり前にその姿を見ながら暮らしていました。
子どもたちも、その暮らしの中で食べるという意味を身体で感じていました。
食べるということへの感謝。“いただきます”という言葉の意味を。
今、こんな時代だからこそそんな鶏飼いの姿を子どもたちに見てほしいのです。
そんなにたくさんは飼えませんが烏骨鶏という種を守っていくためにも必要な仕事だと感じています。